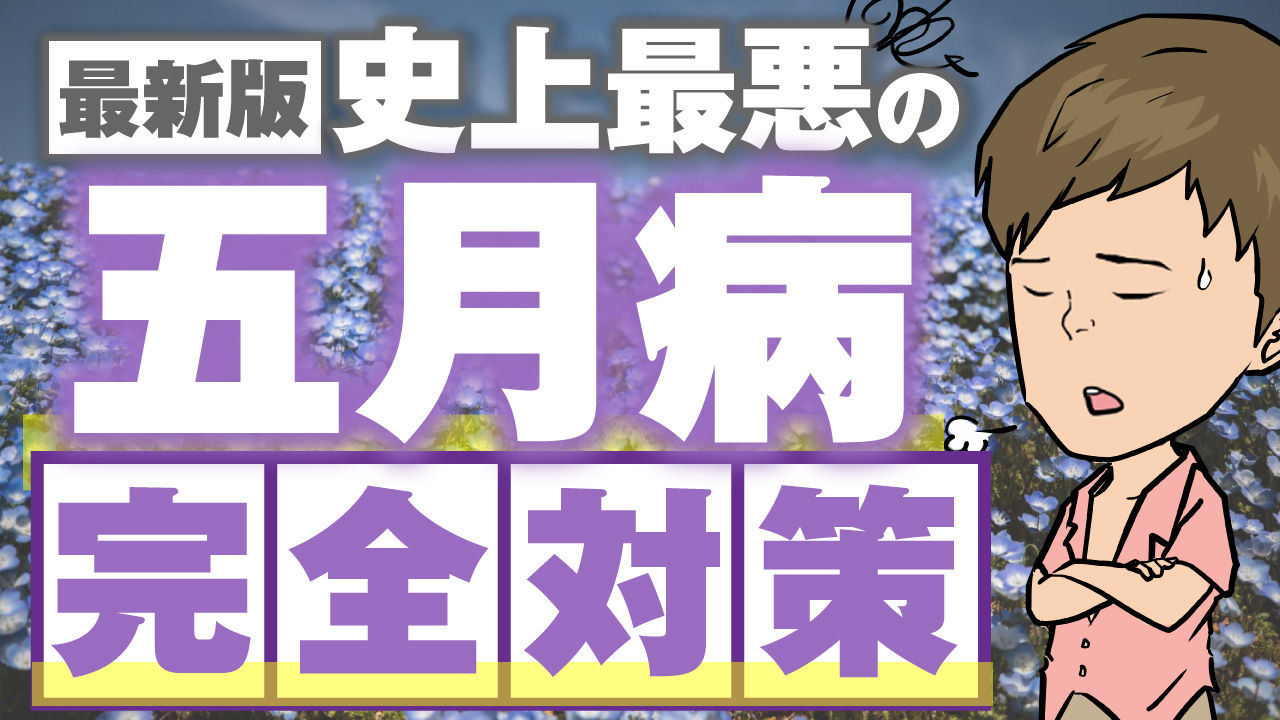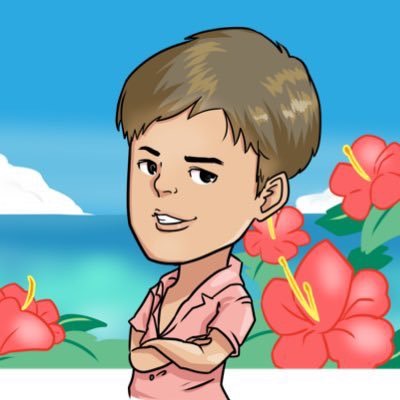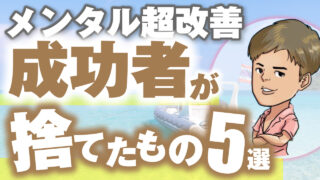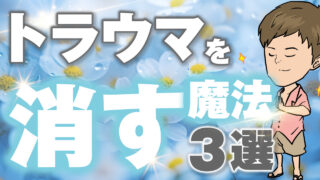こんにちは。ココロの学校・バーツです。
「夜眠れない」
「やる気が出ない」
「朝起きてもダルイ」
「仕事に向かう足取りが重たい」
となんだかしんどくないですか?だけど、もう大丈夫です。
この記事では「五月病対策の完全版」ということで、おそらくどの記事よりも5月病を詳しく、そして2025年版、最新の内容になっています。
今回の記事では、五月病が本当に心配だ…って人のために、①なぜ五月病が起こるのか?②なぜ今年の五月病がキツいのか?③どうすれば五月病から抜け出せるのか?を完全に解説します。
 バーツ|ココロの学校
バーツ|ココロの学校
元々は、超が付くほど強度のHSS型HSP。
大人数や人前で話すのはもちろん、人の感情や思考が気になって仕方ありませんでした。でも、そんな30年苦しんだHSPを自ら克服。
現在は、HSP才能起業家・HSPカウンセラーとして、活動しています。
今年の五月病、過去最高にキツいです。

さて、今年は例年よりもしんどい五月病がやってきます。その背景には、
- 時代のスピードアップ
- 地球レベルでの次元上昇
が起こっており、過去にはなかったストレス度合いが影響します。
こんな悩みありませんか?
こんな違和感をあなたも感じていませんか?
<心の変化>
- 新しい環境に飛び込んだばかりなのに、早くも疲れきってしまった…
- 頑張らなきゃと思うほど、身体が重くなる…
- やる気はあるのに、心がついてこない…
<体調の変化>
- 肩こり
- 頭痛
- 胃の痛み
- 下痢
- 便秘
- 腰のヘルニア
僕のところにも、
「初めての社会人生活で、慣れない通勤、人間関係、覚えることの多さにヘトヘト。家に帰ると、ただ寝るだけの毎日…」
「急にモチベーションが下がって、朝起きるのが辛い。出社の電車で涙が出そう…」
「在宅勤務で自由なはずなのに、誰とも話さない日が増えて孤独感がつらい」
こんな声が届きます。
僕も社会人1年目の5月には…
実は、僕も社会人1年目の5月、同じ状態に陥りました。
希望に満ち溢れ、大手企業に入ったにもかかわらず、最初の一ヶ月が終わった頃にはとてもしんどかったです。
GWがあったので、少し休むことはできたのですが、GWを明けてからというものの、目の前の仕事をこなすだけで精一杯なのに、
「もっと頑張らないと」と毎日自分を責めていました。
しかも、新しい人間関係。
とてもとても心と身体がついてこない日々が続いて、ついには朝寮からオフィスに向かうのがしんどくなりました。
それでも、真面目だった僕は(笑)なんとか自分を奮い立たせて出勤していたのです。
「同期のエリートたちから遅れをとってはいけない」
「こんな入社一ヶ月やそこらで弱ったら、この先何十年もやっていけない」
そう思う日々が続きました。
あの時は「自分が弱いだけだ、強くなれ」と思っていたんですけど、今ならはっきり言えます。
あれは立派な“五月病”のサインだったんです。
放っておくと危険です…
実は、このまま放っておくと、どうなるか?
五月病は一時的な不調と思われがちですが、放置すると「うつ病」や「燃え尽き症候群」に繋がる危険性もあります。
「まあそのうち元に戻るでしょ」なんてやり過ごしているうちに、心と身体はどんどん限界に向かってしまいますから、絶対に放置しないでくださいね。
五月病自体は決して病気ではありませんから、ここだけはしっかり覚えておきましょう。
逆に言えば、静かに忍び寄ってくる前兆をしっかりととらえてあげたらいいのです。
だから、安心してください。
五月病は、ちょっとした習慣の見直しと、正しいメンタルケアの知識があれば、驚くほどに改善できます。
この記事では、
「やる気が出ない」
「眠れない」
「孤独を感じる」
「疲れが抜けない」
といった症状に、【今日からすぐできる具体的な対策】を科学的な根拠も踏まえながらお伝えしていきます。
実際、僕も“あること”を習慣にしただけで、心が少しずつ軽くなって、朝起きるのが苦じゃなくなったり、徐々に五月病にならなくなり、今ではまったく五月病になることがなくなりました。
さらに、これまで僕がこれまでサポートしてきた人たちも
「会社に行くのが怖くなくなった」
「気持ちの波が穏やかになった」
「無理せず、自分らしく働けるようになった」
と、メンタルが安定し、前向きに過ごせるようになったと言ってくれます。
なぜ五月病が起こるのか?

まずは「五月病」の正体と、心が不調になるメカニズムを解説しましょう。
「頑張りたいのに、なんだか気持ちがついてこない…」
「やるべきことが目の前にあるのに、身体が動かない…」
そんなあなたの“うまくいかない”原因は、あなたのやる気が足りないせいではありません。
5月は1年のうち、辛い月です
1年は1月から始まって、1月2月3月って忙しいですよね。
行く、逃げる、去るの1月2月3月ですよ。
それで、年度が変わって、また大きな変化が起きて疲れて、ふと一息つくタイミングがゴールデンウィーク。
そして、GW明けても疲れが取れないってなると、そりゃ体調も崩れますよね。
五月病とは、環境の変化・ストレス・疲労の蓄積により、心や身体がブレーキをかけてしまう状態です。
さっきも言ったように、医学的には正式な病名ではなく、決して病気ではありません。
ただ、これを放置しておくと、うつ状態や自律神経の乱れ、適応障害の初期症状として扱われることになります。
特に、2025年は、新年早々から
- タスクの急増
- 物価高
- 社会不安
など、例年以上にメンタルに僕たち一人一人に負荷がかかっている年になっています。
5月病のメカニズム
新社会人として「早く結果を出さなきゃ」と全力で働いたあなた。
異動で慣れない部署に入り無理して笑顔を続けているあなた。
フリーランスとして自由に働けるはずが、誰とも話さない孤独に疲れ果てたあなた。
あなたは、ずっと気を張り続けていたはずです。
そしてゴールデンウィーク。
やっと少し休めると思ったその瞬間、心と身体が急に脱力し、反動のように無気力になる
これが、五月病のメカニズムです。
なぜか「自分だけがうまくいかない」と感じてしまうことってありますよね。
周りはちゃんと働いてるように見える。
SNSを見れば、友達はキラキラしてる。
自分だけが“落ちこぼれた”気がして、さらに自己嫌悪に陥る。
でも、それはあなただけじゃないんです。
実際、GW明けから6月にかけて、心療内科を受診する人は統計的にも毎年急増しているんです。
根本的な原因は「変化」と「適応疲れ」です。
人間の脳は“変化”に非常に弱い。
新しい環境、人間関係、通勤リズム、仕事内容、生活スタイル…など、あなたは想像以上に多くの変化に適応しようとしてきて頑張っているんです。
この「適応努力」は、目に見えないけれど、ものすごいエネルギーを消耗しています。
その結果、脳や自律神経がオーバーヒートして、心身がブレーキをかけている状態。
これが五月病の正体です。
ここで、もう一度強調したいことは、あなたが今感じている不調は、「怠け」でも「根性がない」からでも「弱い」からでもありません。
変化に対して、真面目に向き合ってきた証拠です。
今年2025年の五月病がキツい

まず前提として、コロナが5類になってもう2年ですよね。
2019年の12月に中国で出てきて、世界的に広がったのは2020年の2月から3月くらい。
ちょうど僕はこの頃に独立しました。
独立していきなりコロナ禍で、別の記事でも話しましたが、本当にお先真っ暗になりました(笑)
で、日本も春先くらいから結構流行って、そこから3年間自粛のような生活が続きましたよね。
僕は海外で起業したので、3年間、日本に帰ることができませんでした。
そういう中で、在宅勤務が広がったり、社会構造が大きく変わりました。
社会のルールが新しくなったり、行動が制限されたり、経済も止まっていました。
そして、2年前5類認定されてから、かなりスピードアップして経済、社会が動き始めて、人の移動も戻ってきて、経済だけでなく、社会構造やテクノロジーも大きく進化しているわけです。
あなたも実感していませんか?
スピードアップに人間がついていけてないのが大きな原因です。
- 社会環境の急激な変化とストレス耐性の限界
- 自律神経の乱れと季節性要因
- 凹んでもすぐに立ち直るしなやかな心
- 細かいことは気にしない大らかな心
社会環境の急激な変化とストレス耐性の限界
これは、東京大学の研究で、新生活開始後1ヶ月以内に適応困難を感じる人の割合が過去10年で最も高い水準にあると報告されました。
特に、2025年は、
- 物価高騰と賃金の伸び悩みによる経済的不安
- リモートと出社の混合スタイルでアイデンティティの不安定化
- SNS普及による比較疲れと情報過多
- コロナ禍明けの反動で再加速する社会への適応負荷
これらの要素が、「ストレスの累積」と「慢性的な緊張状態」を生み、メンタルに大きく影響しているというのです。
自律神経の乱れと季節性要因
慶應義塾大学の医学部で、 5月の急激な気温上昇や湿度変化によって、自律神経が以前よりも乱れやすくなったと分かったそうです。
4月の日中と朝晩の寒暖差、5月上旬の急激な温暖化と梅雨入り前の湿度の上昇。
この天候による原因は、「気象病」とも呼ばれ、交感神経と副交感神経のバランス崩壊につながります。
その結果
- 疲労感
- 不眠
- 集中力の低下
- 無気力
などを増加させ、心の不調に拍車をかけるのです。
Z世代・ミレニアル世代に特有の心理的安全性
早稲田大学では、Z世代やミレニアル世代が 「空気を読むこと」や「自分の気持ちを抑えて同調すること」に強いストレスを感じやすいということを突き止め、
新年度という“同調圧力が強い時期”に、新しい人間関係や空気感に無理して合わせようとすることで精神的に病んでしまうということです。
適応障害の増加
厚生労働省によれば、新卒もしくは、転職者の「適応障害」の診断件数が昨年は13%も増えているとの報告です。
特に、「4月〜6月」の新生活期にはさらに集中することが予想されています。
つまり、五月病は甘え”でも気のせいでもなく、 れっきとした医学的な注意信号と考える必要があるのです。
ただ、病気ではありませんよ。
2025年ならではの構造的なストレス
2025年は、
- 円安
- 物価高による生活費の不安定化
- 働き方改革により「自由」と「自己責任」が増したことによるプレッシャー
- ChatGPTなどのAIツールの普及によるスキル変化への焦燥感
- ITの加速による焦り
と、2025年はこのような独自のストレス要素が、心に重くのしかかって、
「例年以上にしんどい」
「キツい」
と感じる人が増えるのです。
どうすれば五月病から抜け出せるのか?

何度も言いますが、五月病は正式な病名ではありません。
単に、うつ状態や適応障害の初期症状であるとされる程度です。
- やる気が出ない
- 無気力
- 食欲不振 or 過食
- 不眠 or 過眠
- 気分の落ち込みや不安感
- 社会的な孤立感
という症状なわけですが、これは、病気ではなく、自律神経の乱れからくるものです。
自律神経とは、無意識に身体をコントロールしている神経系で、ご存知かもしれませんが、
「交感神経」と「副交感神経」のバランスで成り立っています。
五月病の時は、この「交感神経」と「副交感神経」のバランスがストレスや不規則な生活によって、崩れ、心身が疲れやすくなっています。
なので、
まずメンタルのリセット習慣を知ってください!
これは、日常の中で、意識的に心を整える時間や行動を取り入れる習慣のことです。
心理学では「コーピング(対処行動)」とも言い、ストレスが高まる前に対処できる人ほど、メンタルが安定しやすいとされています。
そこで、今日からできる五月病回避のための具体的な行動習慣を今から7つ紹介します。
- 起きてすぐに日光を浴びる
- 軽い運動を取り入れる
- 生活リズムを一定にする
- 1日1回、気持ちを書き出す
- カフェインの“摂りすぎ”に注意
- 予定を減らす
- 誰かに話す機会を作る
五月病の正体と、メカニズムがわかったところで、ここからは「どうすれば回避できるのか」をしっかり最後まで読んでください。
メモの準備はいいですか?
起きてすぐに日光を浴びる
朝の光には、「セロトニン」という幸福ホルモンの分泌を促す力があります。
これは、脳内のリズムを整えてやる気スイッチを入れてくれる効果もありますので、
朝起きたらカーテンを開けて2〜3分、外に出られるなら5分でもOKなので、日光を浴びてください。
軽い運動を取り入れる
「動けば気分が変わる」は、科学的にも証明されています。
ウォーキングでもストレッチでもヨガでもOKです。
筋肉が動くと、脳内の神経伝達物質も活性化され、自然と前向きな思考になります。
行動活性化理論でも、うつ症状の軽減に効果的な心理療法のひとつで、「まず動く」ことで、やる気・意欲が“後から”ついてくるという仕組みが解明されています。
軽い運動や散歩、習慣①の日光を浴びるといった行動が、脳内のセロトニンやドーパミンを活性化させます。
これにより、「動く → 気分が上がる → また動ける」の好循環が生まれるので、習慣の①と②を大切にしてください。
生活リズムを一定にする
五月病の最大の敵は「不規則な生活」です。
新年度が始まって夜遅くまでの残業や飲み会、そして、SNSやNetflixが要因です。
GWを上手に使って、崩れたリズムを整えたいですね。
それだけで自律神経は安定します。
交感神経優位が続いている場合が、入浴や瞑想などを通じて、副交感神経を優位にする時間を増やし、リラックスモードに導くことが良いと脳波・ホルモン測定で証明されています。
1日1回、気持ちを書き出す
頭の中のモヤモヤを紙に書き出すことで、脳が安心します。
以前の米国流 自己肯定感の上げ方の記事にも書きましたが、これは「ジャーナリング、書く瞑想」と呼ばれ、不安・焦り・混乱の整理に非常に効果的です。
これは、認知行動療法(CBT)とも呼ばれ、科学的にも効果が検証されていますし、
臨床心理の現場でも活用されており、自己肯定感が上がります。
毎日の生活に組み込んでみてください。
僕も必ず寝る前に、その日の振り返りと明日やることを書き出すようにしています。
カフェインの“摂りすぎ”に注意
カフェインは、交感神経を刺激して脳を興奮状態にします。
夜のカフェイン摂取を控えるだけでもメンタルがかなり安定します。
実際、僕は30歳の頃からコーヒーをやめました。
今も昼間はカフェインの入っているお茶や紅茶を飲みますが、午後はカフェインが入ってないものしか飲みません。
これはかなり自律神経が安定するので、試してみてください。
「予定を減らす」勇気を持つ
詰め込みすぎると、心の余裕がなくなります。
ありがちではありますが、自分を大切にする一歩は、手放すことからです。
「何もしない」をスケジュールに書き込んでください。
「誰かに話す」機会をつくる
思っていること、考えていることを口に出すことで、脳の整理が進みます。
家族・友人・上司・相手は誰でもいい。
また、これらの人に話しにくい場合は、カウンセラーなどでも構いません。
自分の中で溜め込んでしまうことが一番良くないことです。
「話すだけ」で心は軽くなります。
僕もこの話せないこと、相談できないことで相当苦しみました。
自分ではわかっていたんですよね。
自分が病んでいることを。
それでも言い出せなかった弱さがありました。
まとめ
ということで、今回のまとめです。
この記事をここまで読んでくださったあなたは、
- どうにか自分の人生を変えたい
- HSPを克服したい
- 生きづらさを解消したい
そういう想いで日々努力されている素敵な人だと思います。
そんなあなたはこの記事を何度も読み返すことで、もっともっと素敵な人生が手に入ります。
今日お伝えした7つの習慣をぜひ日々の生活に取り入れて、過去最強にキツい五月病を乗り切ってくださいね!
無事に乗り切れたら報告をお待ちしています!!
今回は「五月病 完全対策」というテーマで
①なぜ五月病が起こるのか?というメカニズム
②なぜ今年の五月病がキツいのか?ということで、コロナ後の社会構造と経済情勢の話
③どうすれば五月病から抜け出せるのか?ということで、7つの習慣⇩
- 起きてすぐに日光を浴びる
- 軽い運動を取り入れる
- 生活リズムを一定にする
- 1日1回、気持ちを書き出す
- カフェインの“摂りすぎ”に注意
- 予定を減らす
- 誰かに話す機会を作る